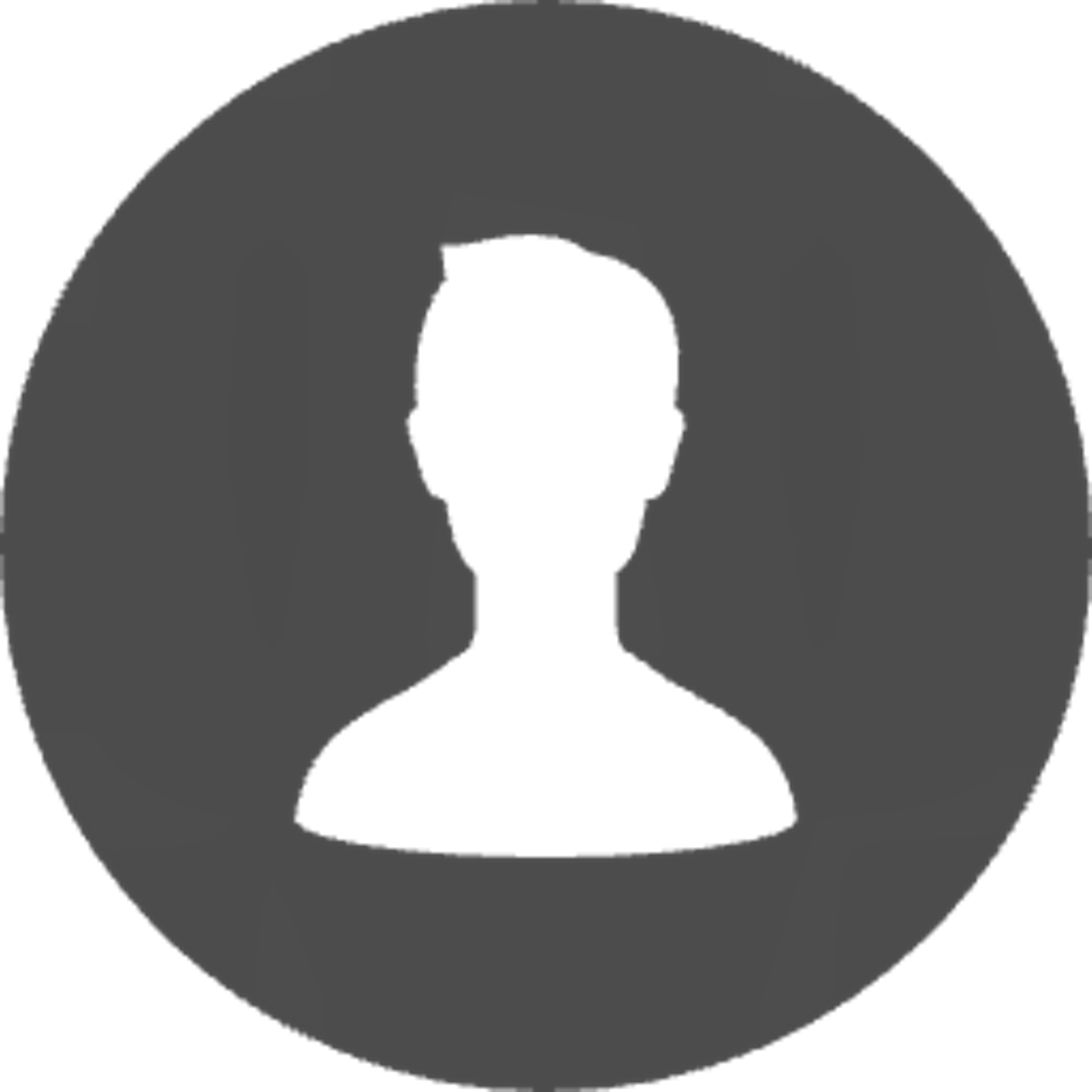メインフレームとは?富士通やIBM,日立の違いやおすすめの案件獲得方法について徹底解説!
z/OS、db2、cics、RACFなどのスキル需要が高騰しているのはご存知ですか?若手不足と高齢化が進む一方、基幹系システムは今も動き続けているからです。
経験者が減少している中、その希少性から高単価・フルリモート・柔軟稼働といった、好条件での募集も増加中。
この状況は再構築・リプレイスが本格化する前の“今だけ”のチャンスかもしれません!メインフレーム人材が案件獲得に必要なスキルについて解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
メインフレームとは?
メインフレームとは、金融機関・官公庁・大手製造業などで利用される、大規模かつ高信頼な汎用コンピュータシステムのことを指します。z/OSなどのOSを用いて、数万〜数十万件のトランザクションを高速かつ安定的に処理できる能力が特徴で、ミッションクリティカルな業務の基盤として長年活用されています。
現在は「レガシー」と捉えられる場面もありますが、その堅牢性・長期運用における実績は他のITインフラでは代替困難なものとされており、今なお多くの企業がメインフレームを中核に据えています。
メインフレームのオープン化とは
メインフレームの「オープン化」とは、従来の専用ハードウェア・OS環境に依存しない形で、他システムとの連携や再構築を進める流れのことを指します。Linuxサーバとの共存や、クラウド基盤との統合、API接続の活用などを通じて、従来の閉じた環境を“開いて”いくことが注目されています。
ただし、すべてをオープン系に置き換えるのではなく、メインフレームの強みを活かしながら、段階的なモダナイゼーションを行うケースが多く見られます。
メインフレームの汎用機とは
汎用機とは、メインフレームの別称であり、多目的かつ複数業務を並行処理できる大規模計算機のことを指します。ひとつのシステム上で会計処理・基幹業務・バッチ処理などを同時に行える設計になっており、まさに企業活動の“心臓部”として機能してきました。
富士通、IBM、日立といった大手メーカーが提供しており、それぞれが独自のアーキテクチャやOSを用いて高性能・高信頼性を追求しています。
富士通/IBMメインフレームの特徴
メインフレームと一口に言っても、メーカーごとに設計思想やOS、操作体系には違いがあります。ここでは、国内外で代表的な3社(富士通・IBM・日立)のメインフレームの違いや、それぞれの強みを整理して解説します。
メインフレーム 富士通の特徴
富士通のメインフレームは「GS21シリーズ」などに代表され、国内企業のニーズに合わせた高信頼・長寿命設計が特徴です。独自OS「OSIV/MSP」や、富士通独自のJCL環境に対応しており、日本企業の業務ロジックに深く組み込まれた導入事例が多数あります。
また、富士通製メインフレームの保守継続期間の長さや、富士通SEとの長期的な運用支援体制も評価されています。公共系・製造業で多く採用されている傾向があります。
メインフレーム IBMの特徴
IBMのメインフレームは「zSeries(z/OS)」で有名で、世界中の金融機関・グローバル企業で標準的に利用されている基盤です。特にトランザクション処理性能に優れ、CICS、DB2、JES、RACFといった高度な機能群が豊富に搭載されています。
グローバルでの運用実績が豊富であることから、英語OSや英語マニュアルへの対応が求められるケースも多いですが、スキルの汎用性・市場価値の高さという点では随一です。
メインフレーム 日立の特徴
日立のメインフレームは「AP8800シリーズ」などが知られ、公共機関や大手製造業、金融業などで根強いシェアを持っています。独自OS「VOS3」や、日立独自の資産運用・資源管理機能が組み込まれており、堅牢性と保守性に優れる点が特長です。
また、他メーカーと比較しても、国内市場に特化した開発体制や保守網の密度が高く、現場でのサポート体制に強みを持つのも日立製のポイントです。
メインフレームの特徴

メインフレームは、安定した稼働性能と、大量データを処理できる力、そして堅牢なセキュリティを兼ね備えた基盤として、今も金融や公共系の現場で重用されています。トラブルが許されない業務を長年支えてきた信頼性があり、高度な信頼性、可用性、保守性(RAS)を必要とされる場面では今尚、選ばれ続けています。
メインフレーム人材になるためにスキル以外に必要な姿勢・考え方
いわゆる“メインフレーム経験者”といっても、求められるのはスキルだけではなく、考え方や姿勢などさまざまです。現場から「このように対応してくれる方なら即依頼したい」と選ばれる方になるために、以下の内容を意識してみるのもいいかもしれません。
1.報連相を徹底し、業務範囲を正しく認識できること
前述の通り、メインフレームは障害の発生により処理が停止した場合に非常に大きな社会的影響が現れる交通機関や金融機関などの基幹システムで、一般にミッションクリティカルなシステムであり、最低限として何があっても停止しないことが求められます。そのため自分の担当領域、担当業務を守ることやトラブル発生の際には、大きな問題へと発展する前に、しっかりと共有や報告を行い対処する必要があります。
2.安定運用を支える“手順化・整備”のスキル
メインフレームの現場では、ミスや属人化が許されない業務が多くあります。そのため、対応フローや操作手順,リカバリ方法などを、明確に「手順化・マニュアル化」できるスキルが非常に重要です。障害対応時や定期作業の中で、「誰がやっても同じように回せる」よう整備する力が必要です。
3.会社の指示や考え方に柔軟に対応する
重要な情報を扱い、社会インフラを支えるメインフレームの運用では、会社の指示に対して、適切に柔軟に対応する必要が求められます。たとえば、トラブルなどにより急な勤務時間の変更や、時として出社対応が求められるなどスキル的な部分だけでなく、業務への向き合い方についての変更を求められることもあります。役割の重要性を理解して、柔軟に対応できると多くの信用や信頼が集まります。

「JCLが読める、RACFに触ったことがある」 それだけで“即声かけたい”と思えるレベルです。 正直、メインフレームの運用経験まである方は 今ほんとに希少なので「もしかしたら出来るかも…!」 って温度感でも“いたら絶対逃すな”って言われています。
メインフレーム案件にチャレンジしやすいスキル
「メインフレームは難しそう…」と思われがちですが、実は今のスキルを“活かしながら”チャレンジできる領域でもあります。以下のようなスキル・経験をお持ちの方は、未経験からでも十分に適応できる可能性があります。
1. インフラ運用の実務経験
メインフレーム環境は特殊ですが、「安定稼働を支える」という本質は他のインフラと共通です。監視、アラート対応、運用手順の実行といった既存のインフラ経験をそのまま活かせる場面が多く、WindowsやLinuxなど、サーバ運用・監視の現場経験がある人は適応しやすい傾向にあります。しかしながら、アプリケーションと比べても、活用されているシーンはミッションクリティカルな基幹システムでありそのひとつ一つの作業により正確性が求められるため注意は必要です。
2.手順書作成やマニュアル整備の経験
メインフレームでは属人化を防ぐため、あらゆる作業に手順化・文書化が求められます。 そのため、普段から作業マニュアルや引き継ぎ資料を整備していた経験のある方は、「整える力」がそのまま強みになります。「誰がやっても同じように回せる仕組み」を作れる人は重宝されるでしょう。
3.厳格な運用ルールの現場で働いた経験
メインフレーム運用では、一つの操作ミスが数万件の処理停止につながることもあります。 そのため、厳しい運用ルール・手順管理が“当たり前”だった環境での経験は大きな強みです。金融機関や公共系など、ルール遵守が求められる環境にいた方は親和性が高いかもしれません。

インフラ経験がある方なら、“やってきたこと”をベースに すんなり入っていけると思います。チャレンジって言っても、 実は“今までの延長線”にあるケースも多いんですよね。
メインフレームとオープン系システムの違い
アーキテクチャの違い:集中型 vs 分散型
メインフレームは、ハードウェアとソフトウェアが密接に統合された集中型のシステムであり、高い信頼性と処理能力を提供します。一方、オープン系システムは、標準化された技術を用いた分散型の構成で、柔軟性と拡張性に優れています。
運用・保守の違い:専任体制 vs 多様なスキルセット
メインフレームは、専任の技術者による運用・保守が一般的であり、特定のスキルセットが求められます。オープン系システムは、多様な技術者が関与しやすく、運用・保守の体制も柔軟に構築できます。
コストと導入の違い:高額投資 vs 低コスト導入
メインフレームは、初期投資や保守費用が高額になる傾向がありますが、その分、長期的な安定性と信頼性を提供します。オープン系システムは、比較的低コストで導入でき、スモールスタートが可能です。
メインフレームの将来性と課題
技術者不足とスキル継承の問題
メインフレーム技術者の高齢化により、スキルの継承が課題となっています。若手技術者の育成や教育体制の整備が急務です。
システムの老朽化とモダナイゼーションの必要性
長年稼働しているメインフレームシステムは、老朽化が進んでいます。モダナイゼーションを通じて、最新の技術との統合や効率化が求められています。
ハイブリッド運用とクラウド連携の展望
メインフレームとクラウドのハイブリッド運用が注目されています。基幹業務はメインフレームで処理し、フロントエンドやデータ分析はクラウドで行うなど、最適な組み合わせが模索されています。
メインフレームの歴史と進化
1960年代:商用コンピュータの黎明期
1960年代、IBMのSystem/360の登場により、メインフレームは商用コンピュータとしての地位を確立しました。これにより、企業の基幹業務を支える中核的な存在となりました。
1980〜1990年代:分散化とダウンサイジングの波
パーソナルコンピュータの普及や分散型システムの台頭により、メインフレームは一時的に市場シェアを減少させました。しかし、その高い信頼性から、金融や公共分野では引き続き重要な役割を果たしました。
2000年代以降:オープン化とクラウド対応
近年、メインフレームはオープン系技術との連携やクラウド対応を進め、柔軟性と拡張性を高めています。これにより、現代のITインフラとの共存が可能となり、再評価されています。
メインフレームの案件/求人 一覧
メインフレーム人材の需要は今、再評価の波に乗って大きく高まっています。慢性的な人材不足や、リプレイスが本格化する前の“今だからこそ”単価や条件も引き出しやすい状態です。こうした売り手市場も、多くのリプレイス完了と共に終わりを迎える可能性が高く、挑戦するには絶好のタイミングと言えるでしょう。