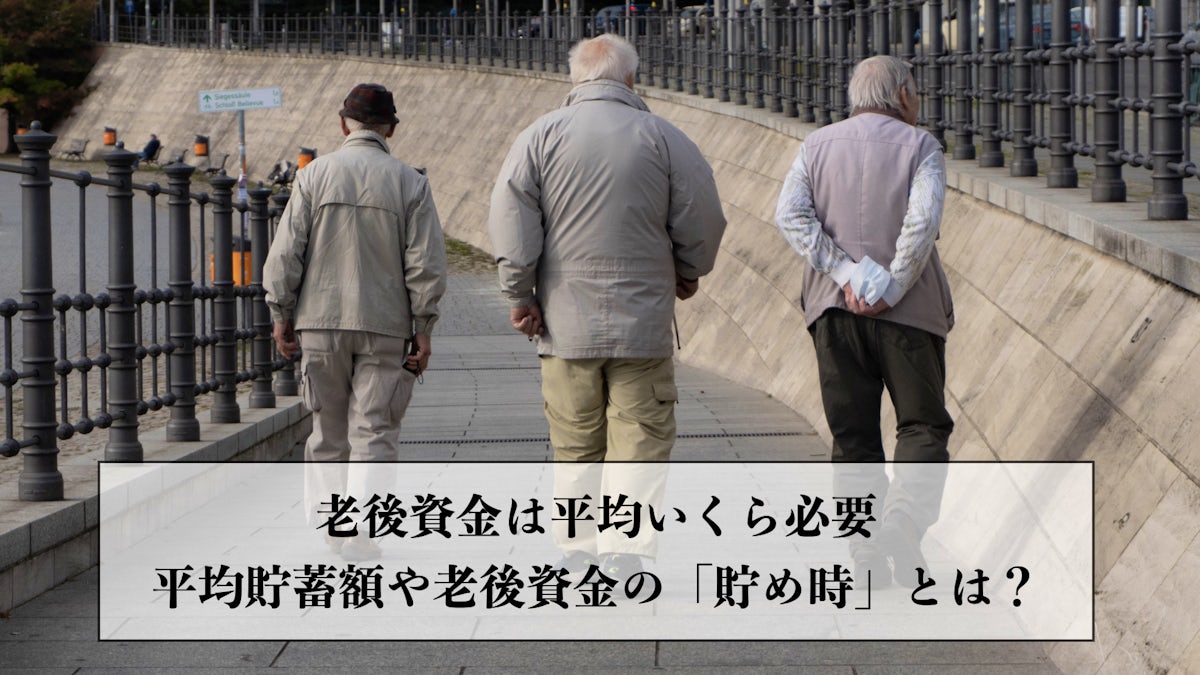
老後資金は平均いくら必要?平均貯蓄額や老後資金の「貯め時」とは?
※当サイトは人材関連サービスを展開する株式会社エイジレスが運営しています。本ページは自社および提携先のPRを含む場合があります。
老後資金にはまとまったお金が必要とはわかっているものの、具体的にどれくらいのお金が必要なのかがわからず不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、そんな不安を解消すべく、年代別の平均貯蓄額や必要な老後資金の計算方法、さらに、老後資金の「貯め時」を紹介します。
資金計画に不安ならFPへ相談を
資金計画に不安がある場合、プロであるFP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。
FPは、相談者の現状やライフスタイルにあわせて最適な資金計画、資産運用や節税などの具体的なアドバイスを提供してくれます。
老後資金2,000万円問題に代表されるように、老後の生活費はひとりあたり数千万円が必要と言われています。
漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。
多くのFP相談サービスがありますが、迷った場合は大手リクルートが運営する『保険チャンネル』への相談がおすすめです。
- 無料で何度でも相談できる
- 会員100万人突破
- 全国47都道府県対応
- 無理な勧誘や営業は一切なし
- 【公式】https://hokench.com/

- 【この記事を読んでわかること】
- 「老後資金には2000万円が必要」は誰にでも当てはまるわけではない
- 世帯全体の平均貯蓄額は1880万円
- 老後資金は「子どもが独立してから定年退職するまで」が一番の貯め時
老後2000万円問題は誰にでも当てはまるものではない

老後資金と聞くと、「2,000万円は必要」というイメージを持つ人も多いでしょう。
2019年に金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が発表した報告書では、「老後の20~30年間に、約1,300~2,000万円が不足する」との試算が示され、メディアでも「老後2000万円問題」として大きく取り上げられました。
結論からいうと、老後資金に2,000万円が必要というのは誰にでも当てはまるものではありません。なぜなら、老後2000万円問題の発端となった試算はごく限定された条件のもとによるものだからです。
例としてモデルケースの一部分を以下にご紹介します。
- 夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯
- 毎月の支出のうち、食費は64,444円
- 毎月の支出のうち、住居費は13,656円
- 毎月の支出のうち、交際費は27,388円
- 臨時支出や臨時収入などは一切含まれていない
上記のデータだけでも、自分の家族構成や家計との違いを感じた人は多いのではないでしょうか。つまり、老後資金がいくら必要かというのは、実際にそれぞれの人が自分の家族構成や家計をベースに算出しなければわからないものなのです。
参考:「家計調査報告(家計収支編)平成29年(2017年)II 世帯属性別の家計収支(二人以上の世帯)|総務省統計局」
老後資金が準備できている人の割合は?平均貯蓄額を確認

必要な老後資金は人それぞれ異なることはわかっても、ほかの人がどれくらいのペースで老後資金を準備しているのかは気になるところです。
ここからは。総務省が2022年5月に公表した「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)平均結果-(二人以上の世帯)」の各データをもとに、世代ごとの貯蓄額や負債額などを確認しながら、老後資金を準備するイメージを膨らませてみましょう。
全体の平均貯蓄額は1880万円
まず最初に、全体の平均貯蓄額を見てみましょう。総務省の「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)平均結果-(二人以上の世帯)」によると、2人以上の世帯における2021年の1世帯あたりの貯蓄額は1,880万円でした。
この金額を知って「そんなに貯金があるの?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。特に学費や住宅ローンなどで出費が多くなりがちな現役世代の人にとっては現実離れした金額に思えるかもしれません。
ここで注意しておきたいのは、この金額はあくまでも「平均」であって、「中央値」ではないということです。さらに、この金額には住宅ローンや車のローンなどの負債も含まれていません。さらに詳しくデータを見てみましょう。
参考:「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)平均結果-(二人以上の世帯)『Ⅰ 貯蓄の状況』|総務省」
平均貯蓄額1880万円以上の世帯は全体の3分の2以下
先ほどもお伝えしたとおり、実際の貯蓄額にはバラつきがあり、すべての世帯に1880万円程度の貯蓄があるわけではありません。以下は、2人世帯以上の世帯の貯蓄の分布です。
| 貯蓄額 | 世帯割合 | |
|---|---|---|
| 4,000万円以上 | 12.8% | |
| 3,000~4,000万円 | 6.7% | |
| 2,500~3,000万円 | 4.8% | |
| 2,000~2,500万円 | 6.4% | |
| 1,800~2,000万円 | 2.7% | 平均貯蓄額 |
| 1,600~1,800万円 | 3.6% | |
| 1,400~1,600万円 | 4.0% | |
| 1,200~1,400万円 | 4.9% | |
| 1,000~1,200万円 | 5.3% | 中央値 |
| 900~1,000万円 | 3.1% | |
| 800~900万円 | 3.7% | |
| 700~800万円 | 3.5% | |
| 600~700万円 | 4.0% | |
| 500~600万円 | 4.6% | |
| 400~500万円 | 4.2% | |
| 300~400万円 | 5.0% | |
| 200~300万円M | 4.9% | |
| 100~200万円 | 5.3% | |
| 100万円未満 | 10.5% |
上記のデータからわかることは、平均貯蓄額とされる1,880万円よりも貯蓄が少ない世帯が67.6%、つまり全体の3分の2以上にものぼるということです。中央値は1,104万円ですので、一部の富裕層が平均を引き上げているといえます。
参考:「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)平均結果-(二人以上の世帯)『Ⅰ 貯蓄の状況』|総務省」
平均貯蓄額の半数以上は預貯金
次に、貯蓄額と貯蓄の種類の構成比について見てみましょう。
| 貯蓄の種類 | 平均 | 保有資産額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~280万円 | 280~726万円 | 726~1,447万円 | 1,447~2,924万円 | 2,924万円~ | ||
| 通貨性預貯金 | 31.1% | 60.6% | 46.5% | 37.3 % | 33.6% | 27.2% |
| 定期性預貯金 | 32.7% | 18.2% | 26.1% | 31.5% | 33.7% | 33.4% |
| 生命保険など | 19.0% | 17.2% | 21.0% | 22.6% | 20.6% | 17.5% |
| 有価証券 | 15.7% | 2.0% | 4.5% | 6.5% | 10.2% | 20.6% |
| 金融機関外 | 1.5% | 1.0% | 1.8% | 2.1% | 1.9% | 1.3% |
ここで言う通貨性預貯金とは一般的な普通預金や通常貯金、当座預金などで、定期性預貯金は決められた期間払い戻しができない定期預金や積立預金などです。
日本は海外に比べて投資への抵抗感を持つ人が多いことで知られていますが、実際に平均貯蓄額の半数以上が預貯金として保有されていることがわかります。
また、保有資産額(貯蓄額)の多い人ほど、株式や債権などの有価証券を持つ割合が高くなっています。資産が多い人ほど、株などでさらに資産を増やしているのかもしれません。
参考:「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)平均結果-(二人以上の世帯)『Ⅲ 世帯属性別にみた貯蓄・負債の状況』|総務省
平均貯蓄額1880万円を超えるのは50代
続いて、年代ごとの貯蓄と負債の平均値について見てみましょう。世帯主の年代ごとの平均の貯蓄現在高と負債現在高は以下のとおりです。
| 世帯主の年代 | 平均 | 40歳未満 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯蓄現在高 | 1,880万円 | 726万円 | 1,134万円 | 1,846万円 | 2,537万円 | 2,318万円 |
| 負債現在高 | 567万円 | 1,366万円 | 1,172万円 | 692万円 | 214万円 | 86万円 |
負債の額は40歳未満でピークを迎え、負債が減少に伴って貯蓄も増えていることがわかります。これには住宅ローンや子どもの学費などが大きく影響していると考えられるでしょう。
また、70歳以上になると貯蓄額が減るのは、リタイアによる収入の減少が考えられます。もちろん個人差はありますが、老後資金は負債が少なくなってくる50代・60代が貯めやすいといえるでしょう。
参考:「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)平均結果-(二人以上の世帯)『Ⅲ 世帯属性別にみた貯蓄・負債の状況』|総務省
負債のうち住宅ローンが占める割合
ここまでのデータを見ると、貯蓄額はまったく負債がないわけではなく、多くの場合、負債ありきの貯蓄であることがわかります。
それでは、負債のうちどれくらいの割合が住宅ローンによるものなのでしょうか。
以下は、先ほどの年代別の貯蓄と負債に加え、負債のうち住宅ローンが占める割合、負債のある世帯の割合、純貯蓄額をまとめたものです。
| 世帯主の年代 | 平均 | 40歳未満 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯蓄現在高 | 1,880万円 | 726万円 | 1,134万円 | 1,846万円 | 2,537万円 | 2,318万円 |
| 負債現在高 | 567万円 | 1,366万円 | 1,172万円 | 692万円 | 214万円 | 86万円 |
| 住宅・土地のための負債 | 513万円 | 1,292万円 | 1,080万円 | 618万円 | 172万円 | 62万円 |
| 負債全体に占める住宅・土地のための負債の割合 | 90% | 94% | 92% | 89% | 80% | 72% |
| 負債保有世帯の割合 | 37.7% | 59.2% | 63.7% | 52.6% | 28.0% | 12.5% |
| 純貯蓄額 (貯蓄現在高-負債現在高) | 1,313万円 | ▲640万円 | ▲38万円 | 1,154万円 | 2,323万円 | 2,232万円 |
40代以降はゆるやかに減少傾向にはあるものの、いずれの年代においても負債のうち住宅ローンの割合が高くなっています。
また、負債のうち住宅ローンが占める割合が減少するのと比例して、負債保有世帯の割合も減少していることからも、多くの世帯で住宅ローンが負債の大部分を占めていることがわかります。
老後資金を無理なく準備するためには、収入に対する住宅ローンの借り入れ額や返済計画が重要なポイントになるといえそうです。
参考:「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2021年(令和3年)平均結果-(二人以上の世帯)『Ⅲ 世帯属性別にみた貯蓄・負債の状況』|総務省
老後資金のリアルな必要金額をシミュレーション

ここまでのデータからもわかるように、負債があるからといって老後資金が準備できなくなるということはなく、老後資金の準備は負債の返済と並行して行っていくものと考える方が自然です。
とはいえ、必要な老後資金の金額を理解しておかなければ、負債の割合が大きくなりすぎてしまったり、老後までに必要な資金が準備できなくなってしまったりする可能性があります。
そこで、ここからは自分にとって必要な老後資金をシミュレーションする方法をご紹介していきます。
1.月々の支出をシミュレーション
まずは月々の支出のシミュレーションをします。子どもがいる人の場合、子どもの独立によって支出が現在とは大きく異なる可能性がありますが、基本的には現在の支出をベースに考えましょう。
老後になってからではなく、現時点で家計を見直し、支出を抑えることができればよりリアルなシミュレーションができ、さらに老後になってからも経済的なストレスを感じることなく過ごせるでしょう。
月々の支出が把握できていない人は、以下の総務省統計局の「家計調査」(2021年)における65歳以上の夫婦のみの無職世帯と、65歳以上の単身無職世帯の消費支出の例を参考にしてみてください。
| 65歳以上の夫婦のみの無職世帯 | 65歳以上の単身無職世帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月平均額 | 構成比 | 月平均額 | 構成比 | ||
| 食料 | 65,789円 | 29.3% | 36,322円 | 27.4% | |
| 住居 | 16,498円 | 7.4% | 13,090円 | 9.9% | |
| 光熱・水道 | 19,496円 | 8.7% | 12,610円 | 9.5% | |
| 家具・家事用品 | 10,434円 | 4.6% | 5,077円 | 3.8% | |
| 被服及び履物 | 5,041円 | 2.2% | 2,940円 | 2.2% | |
| 保険医療 | 16,163円 | 7.2% | 8,429円 | 6.4% | |
| 交通・通信 | 25,232円 | 11.2% | 12,213円 | 9.2% | |
| 教育 | 2円 | 0.0% | 0円 | 0.0% | |
| 教養娯楽 | 19,239円 | 8.6% | 12,609円 | 9.5% | |
| その他の消費支出・合計 | 46,542円 | 20.7% | 29,185円 | 22.0% | |
| 内訳 | 諸雑費 | 18,807円 | 8.4% | 13,369円 | 10.1% |
| 交際費 | 20,729円 | 9.2% | 15,394円 | 11.6% | |
| 仕送り金 | 1,349円 | 0.6% | 387円 | 0.3% | |
| 消費支出 | 224,436円 | 100% | 132,476円 | 100% | |
参考:「家計調査報告(家計収支編)2021年(令和3年)平均結果の概要|総務省統計局」
2.月々の収入をシミュレーション
次に、月々の収入をシミュレーションします。
受給できる年金は会社員や公務員の場合、厚生年金と国民年金の2種類、自営業の場合は国民年金のみです。
厚生年金は保険料の納付月数と収入額から、国民年金は保険料の納付月数から受給額が決定され、50歳以上になると「年金定期便(ねんきん定期便)」で60歳まで加入することを見込んだ上での見込み額を知ることができます。
「年金定期便(ねんきん定期便)」は毎年誕生日の月(1月生まれの場合は誕生月の前月)に日本年金機構より送付されるため、毎年確認をしましょう。
| 平均受給額(月額) | |
|---|---|
| 厚生年金 | 146,145円 |
| 国民年金 | 56,252円 |
上記は厚生労働省が発表している「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」による年金の平均受給額です。「年金の受給金額がよくわからない」という人は、上記の金額を参考にしてみてください。
月々の収入は年金だけではない可能性もあります。定年後も働く予定のある人や、不動産収入がある人などは年金以外の収入を含めて計算しても良いでしょう。
参考:「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省」
3.臨時支出をシミュレーション
老後の生活は毎月の生活費だけで足りるわけではありません。介護や自宅のリフォームが必要になった場合にはまとまったお金が必要になります。子どもがいる人は孫の入学祝いなども必要になるかもしれません。
次のように「どのような老後を過ごしたいか」をイメージしてみると臨時支出にも気づきやすくなります。
- 最後まで今の自宅に住み続けたい:固定資産税・火災保険料・リフォーム費用
- 年に1回は旅行に行きたい:レジャー費
- 子どもに経済的負担は一切かけたくない:介護費用・葬儀費用・お墓の費用
なお、介護にかかる費用や入院・医療費は介護保険や高額医療制度、加入している医療保険でカバーできるものもあります。万が一の際にどのような制度が利用できるかあらかじめ調べておくと、漠然とした老後資金への不安も軽減されるかもしれません。
4.「老後」の期間を設定
「老後」がどれほどの期間になるかは誰にもわかりません。「そんなに長生きできないだろう」と考えて短く見積もってしまうと、老後資金が足りなくなる可能性もあります。 厚生労働省の「令和3年簡易生命表」によると、2021年の日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳ですので、平均寿命よりも10年程度は長く見積もっておきたいところです。
5.老後資金をシミュレーション
月々の支出と収入、臨時支出の合計金額、老後の生活期間が算出できたら、それぞれを以下の計算式に当てはめて必要な老後資金を算出しましょう。
退職金や財産を相続する予定がある人は、必要な老後資金の一部をそれらのお金でカバーできるかもしれません。とはいえ、ゆとりある老後を目指すのであれば、支出は多めに、収入は少なめにシミュレーションしておくことをおすすめします。
資金計画に不安ならFPへ相談を
資金計画に不安がある場合、プロであるFP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。
FPは、相談者の現状やライフスタイルにあわせて最適な資金計画、資産運用や節税などの具体的なアドバイスを提供してくれます。
老後資金2,000万円問題に代表されるように、老後の生活費はひとりあたり数千万円が必要と言われています。
漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。
多くのFP相談サービスがありますが、迷った場合は大手リクルートが運営する『保険チャンネル』への相談がおすすめです。
- 無料で何度でも相談できる
- 会員100万人突破
- 全国47都道府県対応
- 無理な勧誘や営業は一切なし
- 【公式】https://hokench.com/

老後資金は「3度めの貯め時」で貯める!

一般的に、お金は次の3つの「貯め時」を狙うと貯まりやすいと言われています。
- 独身時代
- 結婚して子どもができるまで
- 子どもが独立して自分が退職するまで
先にご紹介した平均貯蓄額のデータで、負債(おもに住宅ローン)が減少する年代で貯蓄額がアップしていたことからもおわかりのとおり、老後資金はこの3つの「貯め時」のなかでも3度めの「子どもが独立して自分が退職するまで」のタイミングが最大のチャンスといえます。
1度めや2度目の「貯め時」でマイホームや子どもの学費のための資金を貯め、3度めの「貯め時」で老後資金を貯めるというわけです。
子どもが独立すれば、それまで必要だった学費をそのまま貯金に回すことができますし、「万が一のとき子どもに苦労をさせないために」と多めに設定していた生命保険の掛け金も見直すことができるかもしれません。
自分に必要な老後資金を把握したうえで、自分が今ライフステージのどのあたりにいるのかを客観視できれば、必要以上に不安に駆られることなく老後資金について考えられるでしょう。
まずは自分に必要な老後資金を知ることから

貯蓄の平均額だけを見ると現実とのギャップに戸惑いを覚えがちですが、データをよく見てみると、実は負債ありきの貯蓄であったり、一部の層が平均を引き上げていたりと、知らなかったことも見えてきます。
数字を見て漠然とした不安を抱えていても、お金が増えることはありません。まずは自分にとって必要な老後資金の金額を知り、そのために今何ができるのかを建設的に考えていくことから始めてみましょう。
▼老後資金に関連する記事はこちら

老後資金の貯め方5つを紹介!計画的に老後資金を貯めるには
年金が老後資金の柱として安定しなくなった現代では、老後に5,000万円必要とも言われています。老後資金を確保しなければいけないとわかっ

老後資金はいくらあれば安心できる?ゆとりある暮らしの作り方
ギリギリではなくゆとりを持った老後の暮らしには、老後資金はいくらあれば安心できるのでしょうか。老後資金を用意する必要があるとはわかって






